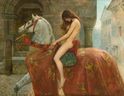- アダムとイブ
「アダムとイブ」とは、『旧約聖書』「創世記」に記された、神が創造した最初の人類の男女です。(解説記事:「アダムとイブ」とは?)











-64x96.jpg)



- マリアの結婚
3歳の時から神殿へ預けられ、身も心も清く正しく育ったマリア(聖母マリア)は、14歳の時(または12歳、諸説あり)、天使のお告げにより、主がみしるしを与えた者を夫とすることとなった。
天使は神殿の大司祭にこう伝えていた。「国中の独身者に一本、杖を持たせて集めよ。杖の先に花の咲いた者がマリアの夫だ」。ダビデ家の子孫で大工のヨセフ(ナザレのヨセフ)が杖を持って神殿に入り、祭壇に杖を置くと、ヨセフの杖だけ花が咲くという奇跡が起きた。そのためマリアの夫となる者が誰の目にも明らかとなった。ヨセフは自分が高齢でありマリアとの年齢差があまりに大きいために辞退しようと考えたが、説得を受けた。ヨセフは司祭の前でマリアの手に結婚指輪をはめ、二人は夫婦となった。





- 受胎告知
キリスト教の聖典である新約聖書に書かれているエピソードの1つで、一般に、処女マリアに天使のガブリエルが降り、マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを告げ、またマリアがそれを受け入れることを告げる出来事です。

























- 聖母
聖人 (せいじん) の母。キリスト教で、イエス= キリストの生母マリアの尊称。




























- 悔悛するマグダラのマリア
マグダラのマリアは新約聖書に登場する、自らの罪を悔い改めキリストに付き従った聖女です。聖母マリアと混同を避けるため、出身地「マグダラ」を前に冠して「マグダラのマリア」と呼ばれています。
キリストが磔刑(たっけい:はりつけの刑)され、三日後に復活して天へと昇った後、彼女は兄のラザロと姉のマルタと一緒にフランスのマルセイユへと渡りました。そこで布教活動を行い、晩年には洞窟で隠遁生活を行いました。その生活は30年余り続き、亡くなったとされています。十字架と頭蓋骨を前にし、自らの罪を悔悛する主題は人気があり、多くの画家に描かれています。
福音書には「マグダラのマリア」と特定されていない女性が何人か登場します。それらの中で、富と美貌によって快楽に溺れ、娼婦をも意味する「罪深い女」が、カトリック教会では一時期、マグダラのマリアと同一人物視されてきました。(現代では、別人とする見方が有力です。)キリストと出会った事で自らの罪を深く悔い、共に伝道の道を歩みました。彼女はキリストの足に涙を落とし、自らの長髪で拭い香油を塗ったとされています。そのため、絵「悔悛するマグダラのマリア」には彼女のアトリビュート(神像・人物像などで、その神格や人物を表すのに不可欠とされる特徴や持物)である香油壺がよく描き入れられています。
















- 聖カタリナ
アレクサンドリアの聖カタリナは、ローマ・カトリックでは伝統的に『十四救難聖人』の一人。ジャンヌ・ダルクと話したとされる聖人の一人です。彼女の生涯は、実在と伝説の狭間にあります。祝日は11月25日。
カタリナはエジプト・アレクサンドリア知事コンストゥスの娘。彼女は当時最高の教育を受けました。カタリナは両親に向かって、「名声、富、容姿と知性で自分を超える男でなければ結婚しない」と宣言していました。
カタリナの母は秘密裡にキリスト教に改宗しており、娘をキリスト教の隠者の元へ送りました。その隠者はカタリナに「その方の美は太陽の輝きよりも勝り、知性は万物を治める。富は世界の隅々にまで広がっている」と説いたといいます。彼女は洗礼を受けキリスト教徒となり、幻想の中で天国へ運ばれ、そこで聖母によってキリストと結婚させられたといいます(神秘の結婚)。
皇帝を訪問したカタリナのことは、ローマ皇帝マクセンティウスの元にも届き、彼女は皇帝に「キリスト教徒を迫害するやり方は間違っている」と説こうとしました。伝説では、カタリナは皇后を改宗させることに成功し、皇帝が送り込んだ50人の異教の賢者たちを論破したため、彼らの多くはすぐに殺されてしまいました。
その後,皇帝はカタリナを口説き失敗すると、彼女を牢に入れました。彼女は車輪に手足をくくりつけられて転がされるという拷問を受けることになりましたが、カタリナが触れると車輪は壊れてしまい、彼女は斬首刑にされました。このことから、彼女の第一の象徴となるのは釘打ちされた車輪で『カタリナの車輪』として知られるようになりました。
伝説では後に天使がカタリナの遺体をシナイ山に運んだといいます。そこには6世紀に東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世によって建立された聖カタリナ修道院があり、今でも残っています。












- ユディト
宗教絵画で女性が男性の生首を持っていたら、ほぼ間違いなくユディト(JUDITH)かサロメ(Salome)。その手に剣があればユディト、皿の上に首を載せていればサロメ、というのが西洋絵画のお約束です。
ユディトは、紀元前2世紀頃に書かれた旧約聖書外典に登場する美女(未亡人)。彼女の住むユダヤの町ベトリアに、敵国アッシリアの将軍ホロフェルネスが軍を率いて侵攻。町は降伏の危機に瀕するが、ユディトが侍女を伴って敵陣に赴き、ホロフェルネスを誘惑して彼の寝首を掻かいて持ち帰ります。頭領を失った敵軍は敗走。ユディトはその美貌でユダヤ民族を救った女傑です。









- サロメ
宗教絵画で女性が男性の生首を持っていたら、ほぼ間違いなくユディト(JUDITH)かサロメ(Salome)。その手に剣があればユディト、皿の上に首を載せていればサロメ、というのが西洋絵画のお約束です。
サロメは、パレスチナに一世紀頃実在したとされる女性です。新約聖書の中に登場し、ヘロデ王の妻ヘロデアの娘との表記のある女性がサロメです。実は新約聖書の中にはサロメの名の記載は一切ありません。なぜサロメだと断定されるのかといえば、古代イスラエルの著述家が著した『ユダヤ古代記』に、両親などの名が同じである人物が登場し、この女性の名がサロメだからです。
(解説記事:サロメ)




-88x96.jpg)






- スザンナと長老たち/スザンナの水浴
主題は『旧約聖書』の「ダニエル書」で語られているスザンナの物語から取られている。
ヘブライ人の裕福な夫ヨアキムの貞淑な妻であったスザンナは毎日のように庭の泉で水浴びをしていました。ところが2人の好色な老人が彼女の美しさに目を付け、スザンナに言い寄る機会を狙っていたのです。その日もスザンナは召使に戸口を固く締めさせて、庭の泉で水浴びを始めた。すると召使たちがいなくなったのを見計らって庭に隠れていた長老たちが現れて、スザンナを脅迫しながら関係を迫った。スザンナはこれを拒否したため、後日、この長老たちはスザンナを姦通罪で告訴し、彼女は死刑判決を受けました。なんということでしょうか、たいした調べもなしに彼女は逮捕されたのです。長老という地位が、人々を信じさせたのです。彼女が姦淫の罪を着せられて処刑されそうになった時、彼女は神に祈りました。
すると、ダニエル(霊体)という少年が長老たちに異を唱えました。彼は長老たちが互いに相談や会話できないように引き離したうえで別々に尋問したのです。「スザンナと若者は、どんな樹の下で密会していたのか?」と。すると、1人の長老は「乳香樹」、もう1人の長老は「カシの木」と別々の樹名をあげたのです。「乳香樹」は低木ですが、「カシの木」は高木で、その大きさには違いがあります。2人の長老たちの主張は虚偽とわかり、スザンナの純潔は証明されました。もちろん、この2人の長老たちは石打ちの刑に刑され、スザンナは解放されたという。





.jpg)









 /
Home
/
Home











-64x96.jpg)




































































































-88x96.jpg)











.jpg)